2013/8/13
カテゴリー » エッセー
「羮に懲りて膾を吹く」
「あつものにこりてなますをふく」と読みます。
これは『楚辞』の「九章」の中の「惜誦」と題する詩の一節です。
この後に「なんぞ此の志を変ぜらんや」と続いています。彼、屈原は危機にある楚の国を憂い、祖国を誤らす佞臣を憎み、彼の堅持した孤高の心情を情熱的に歌ったものです。
熱い料理で舌を火傷した人は、すっかり懲りてしまって冷たい料理でもフウフウ吹いてしまう・・・という意味で、現在では「一度失敗してしまうと必要以上の用心をしてしまう」という臆病な人のたとえに使われています。
失敗は誰にでもまたどこの国にもありますが、失敗を教訓として同じ過ちは繰り返してはいけないのです。楚の屈原のように、「前の失敗」を絶対に忘れてはならないときは、たとえナマスであって吹くのは大事なことだと思う。
毎年、終戦記念日が近づくと、マスコミはこぞって「前の失敗」を繰り返し報道する。終戦68年を経てなお、アツモノを思い出させるためであろう。
「喉元過ぎれば熱さを忘れる」という諺通りの勇ましい人たちもいます。彼らは「アツモノなどへっちゃら」と周囲をあおり立てる。同調者が増え熱狂すると「アツモノでも熱くない」と幻想する結果となりまた同じ失敗を繰り返してしまう。
「アツモノ」とは戦争のみではない。「原発事故」というアツモノにもまたナマスを吹き続けねばならない。「羮に懲りて膾を吹く」という慎重さは「憲法9条を守る」ことにとって極めて大切である。決して臆病者ではない。
― posted by 大岩稔幸 at 01:00 am
2013/5/2
カテゴリー » エッセー
周囲からそれなりの信頼を得るには20年かかる。
「信頼を得るには20年、失うには5分」 ビジネス書などでおなじみの言葉です。胸に手を当てると、誰しも思い当たる節があるであろう。
正確には、「周囲からそれなりの信頼(reputation)を得るには20年かかる。だが、その信頼はたった5分で崩れることがある。
そのことを頭に入れておけば今後の生き方が変わるはずだ」
この言葉は、世界最大の投資持株会社の会長兼経営責任者であるウォーレン・E. バフェットの名言である。
Microsoft社のビル・ゲイツ会長と毎年のように世界一位の富豪の座を争っている人物で、82歳の現役投資家、経営者です。
その投資哲学と運用成績から、居住地の米国ネブラスカ州オマハにちなんで「オマハの賢人」とも呼ばれています。
この場合の20年は象徴的な数字ですが、「信頼を得て保ち続けるには、ちょっとやそっとの覚悟では足りないぞ」という賢人からのアドバイスであろう。
信頼は周囲から寄せられる「未来への期待」
「信用」と「信頼」はどう違うのであろうか。
よくいわれるのは、「信用」は実績の客観的評価であり、その信用を根拠にその人や物が将来も安定して信じられるという感情が「信頼」だとされている。
つまり、信用は自ら築いた「過去の成績」だとすれば、信頼は周囲から寄せられる「未来への期待」であろう。
人や物の未来を切り開くには、長い年月を掛けて実績を積み上げ、周囲からの評価や支持を獲得することが必要である。
しかも、いったん信頼を得たとしても「5分で崩れる」可能性があるわけだから、信頼を「維持」する努力が常に求められるのである。
ウォーレン・バフェットも失敗しないわけではないが、彼は投資上の失敗を公にすることで損失を最小限に抑え、信頼の失墜を防いだそうです。
一旦失えた信頼は、それを取り戻すためには涙ぐましい努力と時間が必要です。
ちょっとやそっとの努力では足りません。何倍もの努力のエネルギーが必要です。
「信用」と「信頼」はどちらも維持して大切にしなければなりません。

ボストンタマシダ
― posted by 大岩稔幸 at 09:14 pm
2013/3/19
カテゴリー » エッセー

「経世済民(けいせいさいみん)」の語源は中国の古典。正確には古い漢字で「經世濟民」と書き、「世を經(おさ)め、民を濟(すく)う」が本来の含意です。
つまり治世全般、いわば政治そのものを指すのが「経世済民」の含意であり、英語の「economy」の訳として使われる現代の「経済」とは本来異なるものです。
東晋(4世紀)時代の思想家である葛洪(かつこう)の著作に「經世濟俗」という言葉が登場し、「經世濟民」とほぼ同じ意味で使われていました。
隋(6世紀末から7世紀初頭)代の思想家である王通(おうとう)の著作には「皆有經濟之道、謂經世濟民」と記され、「經濟」が「經世濟民」の略語として用いられています。
以後、近代に至るまで、中国における「経世済民」「経済」の含意は、治世そのもの、政治そのもの。清朝末期(19世紀)の科挙(かきょ、言わば国家公務員試験)の「経済特科」という科目においても、「経済」は本来の意味で使われています。
中国の古典を学んだ日本の思想家や学者、政治家も、江戸時代末期まで本来の意味で「経済」を理解していたようです。
18世紀前半の日本の思想家である太宰春台(しゅんだい)の著作「経済録」(日本で初めて「経済」という単語が著作名に登場した書籍)には、「凡(およそ) 天下國家を治むるを經濟と云、世を經め民を濟ふ義なり」と記されている。
まさしく、「経済」を「治世」と定義しています。 一方、19世紀前半の思想家である正司考祺(こうぎ)の「経済問答秘録」には「今 世間に貨殖興利を以て經濟と云ふは謬なり」という一文が登場。
「経済」は「貨殖興利」という捉えられ方が浸透しつつあったことを逆説的に裏付けています。 幕末期になると英国から古典派経済学の文献が流入。「経済」の訳語を巡って興 味深い事実が確認できます。
日本で最初に公式に英語を学び、「英和対訳袖珍辞書」を編纂した堀達之助(幕府通訳詞)、日本で最初の西洋経済学の基本書である「経済小学」を刊行した神田孝平(たかひら)、幕末に「西洋事情」を出版した福沢諭吉、いずれも「経済」 を「Political Economy」と紐づけています。
つまり、この時期までは「経世済民」と「貨殖興利」が混在しつつも、博学な学者や思想家は「経済」の本来の意味を理解していたと言えるようです。
しかし、明治維新に伴う近代化、殖産興業ブームの過程で、「経済」は徐々に「貨殖興利」の方に重きが置かれ、やがて「Economy」の訳語が「経済」となり、その訳語が清朝(中国)にも逆流。とうとう中国古典の「経済」の含意は、中国でも歪曲したと言われています。
「経済」大国、「経済」立国の日本。「経済」の含意、本来の意味について、深く考え、政策課題に向き合うことが必要です。
貨殖興利
TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)やアベノミクスを巡って経済論争が喧(かまびす)しい日本。その経済論争の「経済」は如何なる含意で使われているでしょ うか。
3月15日、安倍首相はTPP交渉参加を表明し、担当大臣がTPPに参加した場 合の「経済」への影響試算を公表。この場合の「経済」は「国内総生産(GDP)」 のことを指しています。
試算はTPPに参加する場合と参加しない場合を比較し、10年後のGDPの差額を計算 したもの。「例外」分野の予想はできないため、TPP参加11か国との間で「聖域なき関税撤廃」が行われた場合の仮定計算です。
試算によれば、日本の年間GDPは実質3.2兆円(0.66%)増加する一方、国内農林水産生産額が3兆円減少。 計算方法の詳細や前提条件がよくわからないため、試算の信憑性、正確性、信頼度も現時点では何とも言えません。しっかりと検証しなくてはなりません。
今後の交渉で「例外」分野がどうなるのか、関税撤廃や税率調整のプロセス、サービス自由化や知的財産権の取り扱いなど、不確定要素が多すぎるため、この試算によってTPP参加の是非を判断することは難しいでしょう。
それにしても国内農林水産生産額が3兆円減るというのは気になります。日本が輸入する農産物等には高い関税(例えば牛肉は38.5%)がかかっており、それが撤廃されれば外国産農産物等の輸入が増加。それにつれて国内生産額が減少するという構図です。
外国産の安い農産物や加工食品が輸入されれば、食費軽減を通じて家計に恩恵が及びます。しかし、米、牛肉、小麦などを「例外」分野とすることが政治的争点となっており、「例外」が多くなればなるほど家計の恩恵は減少します。
食品安全基準が緩むリスクが指摘されているほか、食料自給率という食料安全保障の観点からは問題があります。
賛成派、反対派双方が持論を展開していますが、それぞれに真実と誇張と仮定が含まれています。個人的には、そうした論争の真贋よりも過去半世紀の日本農政の構造問題に関心があります。
日本の農業はなぜ競争力が低いのか、競争力を高める農政をなぜ行ってこなかったのか、そして行おうとしないのか。そのことが日本の農政問題の本質です。競争力の源泉がコストであると考えれば、日本農業の高コスト体質の原因とも言っていいでしょう。
例えば肥料。そこに典型的矛盾と問題の本質が垣間見えます。高い肥料を使わせる農協、それを供給する経団連傘下企業。農協はTPP反対、経団連はTPP賛成。
この構図には「農家」や「農業生産者」は登場しません。「農家」や「農業生産者」の高コスト体質を誘発しているのはTPP反対派の農協とTPP賛成派の経団連。 関係者は問題の本質を理解しているはずです。
TPP参加は、こうした構図の中に置かれている「農家」や「農業生産者」にどのような変化をもたらすのか、食費以外の要素を含む総合的な家計の恩恵はどのようなものなのか。
「経世済民」の本来の趣旨に照らせば、これらの点を明確にすることが求められます。日本の農政の積年に亘る問題を放置したままのTPPであれば、その「経済」 連携は、「経世済民」ではなく、所詮、賛成派と反対派の「貨殖興利」にとどまります。
中銀プット
マーケット関係者の間で「バーナンキプット」という単語が飛び交っています。 新語・造語好きのマーケット。一般の人にはわかりにくい世界です。
「プット」はプット・オプションの「プット」。金融派生商品(デリバティブ) のひとつであるプット・オプション(一定価格で売る権利)は、証券(株や債券) や為替の値下がりに備えたリスクヘッジ手段です。
「バーナンキ」は米国の中央銀行であるFRB(連邦準備制度理事会)議長の「バーナンキ」。「バーナンキ議長を売る権利」とは妙な造語ですが、意味は違います。
大胆な金融緩和を断続的に行い、株価を下支えする発言を繰り返しているバーナンキ議長。つまり、バーナンキ議長自身がリスクヘッジ手段と言えるような状況 となっていることを比喩して「バーナンキプット」と言っています。
欧州でも大胆な金融緩和が継続。日本でも緩和派の新日銀総裁が来週20日に就任。 日米欧はQE(Quantitative Easing、量的緩和)レースの渦中にあります。
「バーナンキプット」ならぬ「ドラギ(欧州中央銀行<ECB>総裁)プット」という言葉も使われていますので、早晩「黒田プット」という造語も出てくるでしょう。
要するに「中銀(中央銀行)プット」。中央銀行の金融緩和、あるいは中央銀行 そのものがリスクヘッジ手段になっているということです。
しかし、米国ではジャンク債市場やLBO(買収相手の資産を担保にした借入れによる企業買収)ファンドに大量の資金が流入。2006年当時の住宅バブル時と同様に、 FRBが信用バブル(行き過ぎた金融緩和)に気づいていないと指摘する向きもあります。
翻って日本。この局面、金融緩和は続ける必要があります。株高も円安も歓迎すべき状況。但し、円安はあまり行き過ぎると、原燃材料の輸入コスト増加が企業や家計にマイナスの影響も与えます。
政策には必ず長所(メリット)と短所(デ メリット)があり、それを冷静に認識し、バランスさせることが必要です。
株高も円安も、1990年代から続くデフレと景気低迷の脱却策としての金融緩和の副産物。本来の「目的」はデフレ脱却と景気浮揚。政策には必ず「目的」と「手段」があり、それを混同してはいけません。「中銀プット」はあくまで「手段」。
「目的」はデフレ脱却と景気浮揚ですが、本質的な「目的」は「経世済民」。金融緩和の副産物としての株高と円安が「世を経(おさ)め、民を済(すく)う」 ことにどのようにつながるかがポイントです。
家計や将来世代に恩恵が及び、財政赤字の削減(将来世代の負担軽減)や産業イノベーション推進、硬直化した既得権益の改革等にどのようにつながるのか。積年の日本の問題解決にどうつながるのか。それこそが重要です。
しかし、マーケット関係者にとっては価格下支えが「目的」で「中銀プット」は 「手段」。マーケット関係者の主眼は「貨殖興利」であって、第一義的には「経世済民」ではありません。
人為的な「中銀プット」に副作用はつきもの。異例の金融緩和の本質は時間的余裕を確保する時間軸政策。確保した時間で手を打つべきことは、積年の日本の問 題解決策。
金融緩和が終わっても成長できる日本を構築することです。 「中銀プット」が単なる「貨殖興利」に終わらないように国会で十分に議論してほしい。
― posted by 大岩稔幸 at 12:15 am
2013/1/2
カテゴリー » エッセー

昨年末に新政権が誕生しました。
山崎さんの言葉に「政府は期待するものではなく監視するもの」というのがありました。
新政権に関して、とくに、どういったところを監視していけばいいのでしょうか。
期待せずに監視する対象は、政治というよりも政府でしょうね。その意味で、まず大切にしなければならないのは憲法です。これは、現在の日本国憲法を墨守せよという意味です。このことが今年の課題です。
一般論として、憲法というのは、そもそも政府を監視するための法律であることを国民が今一度理解しておく必要があるということです。
憲法は、 国家権力が個人の自由に介入しないことを目的として定められたものです。
では、その憲法の精神に則り、誰がどのように政府を監視していくのかといえば、やはりマスメディアの役割が大きいと思います。
私達は日々の生活に忙しくて、政府を継続的に監視することはできません。果たして、日本のマスメディアは、ウォッチ・ ドッグとして機能しているのでしょうか。それは、どうもそうではないようです。
2012年の出版界の一つの特徴はメディア批判本であったように思います。
まず、1月17日に元日本経済新聞記者の牧野洋氏の「官報複合体 権力と一体化する新聞の大罪」(講談社)が出版されました。
2月25日には、元共同通信記者の青木理氏、「ビデオニュース・ドットコム」を主宰されている神保哲生氏、そして元北海道新聞記者の高田昌幸氏の共著として「メディアの罠 権力に加担する新聞・テレビの深層」(産学社)が出版されました。
さらに、7月4日にはニューヨーク・タイムズの 東京支局長、マーティン・ファクラー氏の「「本当のこと」を伝えない日本の新聞」 (双葉新書)が出ました。
つい最近も、12月3日に前述の牧野氏と衆議院議員の河野太郎氏の共著として「共謀者たち 政治家と新聞記者を繋ぐ暗黒回廊」(講談社)が 出版されました。
こうした本のサブタイトルをみれば、本の執筆動機は明らかでしょう。本来は、権力の監視役としての役割を期待されているマスメディアに対する強い危機感です。こうしたメディア批判本が2012年に集中したことには理由があると思います。
それは、東日本大震災、特に原発事故の報道により、執筆者達の危機感が閾値を超えたということでしょう。これは、発言せざるを得ないと。
ところで、こうした本はどの程度の読者に読まれているのでしょうか。Amazonのランキングをみると、「官報複合体」は102476位(12月18日現在)です。この本は、たいへんな力作であると思ったのですが、売れ行きはあまり芳しくないようです。
「メディアの罠」は、75404位(同)です。これも非常に勉強になる本でしたが、あまり 本屋で見かけることはありません。この両著の書名と著者の名前で記事検索をかけましたが、主要日刊紙では一度も紹介されておりません。
メディア批判本の宿命といえば宿命でしょうが、マスメディアで紹介されないのです。
結局、こうした問題意識が 広く国民に共有されることはありません。
本の内容を、この欄で紹介するときりがないので、興味のある方はお読みください。 こうした問題意識を共有することからも、政府の監視が始まるのではないかと思います。
ウォッチドッグ
別名:ウォッチドッグタイマー
【英】watchdog
ウォッチドッグとは、システムが正常に動作しているかどうかを監視するためのデバイスの総称である。
ウォッチドッグは、システム上で動作しているそれぞれのアプリケーションに定期的に信号を送らせている。一定周期を経過してウォッチドッグに信号を送らなかったアプリケーションがあれば、そのアプリケーションがハングアップなどの異常状態に陥っていると判断し、CPUに割り込みをかけてアプリケーションを停止したり再起動したりする。
また、インターネット上のウェブサイトを監視するツールのことをウォッチドッグと呼ぶこともある。この場合のウォッチドックでは、定期的に監視先のウェブサイトをアクセスしたり、そのレポートをオンラインで閲覧することができるようにしたりしている。
― posted by 大岩稔幸 at 09:11 pm
2013/1/1
カテゴリー » エッセー

屋久島 神代杉
未来を信じて
日本には強くなってほしい。このところ切実にそう思う。もちろん軍事力のことではない。核兵器などという使えもしない装備で国を守ろうとするのは北朝鮮レベルの弱い国だ。
核兵器以上に「侵しがたい」と思わせるもので防衛されなくてはならない。強い国とは、外に向かって打って出る力のことではなく、この「侵しがたい」何かによって守られている国のことだ。
外側から「侵しがたい」と思わせるものは、自国民によってまず、日本の、日本人のアイデンティティーとして、意識されなくてはならない。
戦後の日本には、とりあえず経済力があった。エコノミックアニマルなどと嫌悪されても、お金を持っていることは強かった。けれど中国の台頭により、このアドバンテージは失われた。
私は失われたとは思っていないけれど、そう考える日本人は多いと思う。経済力を一国の数値で比較すれば、国内総生産(GDP)で中国に追い抜かれ、今後も回復は難しいだろうが、経済力が何のために必要かと言えば、個人の生活を豊かに平安に保つためだ。
GDPを一人アタマに換算して中国に追い抜かれたときは、負けを認めなくてはならないが、国家単位でしか経済力を見ることができない人にとっては、日本はすでに追い抜かれてしまったのだろう。
人口が十倍の国には、優れた人間も劣った人間も十倍いる、という自明のことを忘れ、怯(おび)えたり驕(おご)ったりするのは愚かなことに思える。
いっときも早く日本人は、新たなアイデンティティーを持たなくてはならないが、そのためには、もっと地に落ちる必要があるのかも知れない。持てるものをすべて失ったとき初めて、自分たち日本人の身に備わったDNAが自覚される、ということに期待したくなる。
日本人は、歴史的な権力の委譲である明治維新において、江戸城を無血開城した国民である。二つの原爆を落とされ、無条件降伏をしたあとのアメリカによる占領に、憤怒を隠して服従したかといえば、「過ちは繰り返しませぬから」と主語の無い反省の言葉を原爆慰霊碑に刻み、アメリカへの報復を考えなかったどころか、魅了されていった。
アメリカの占領政策がうまかったとはいえ、これが中国や韓国であったなら、恨みは世代を超えて末代まで継承されたに違いない。表面的に屈することで、内なる炎は身を焼いただろう。
この日本人の淡泊さを「忘れやすい平和ボケ」だとネガティヴに考えることには私は反対である。ことが決着したあとはすべてを水に流す、実はこれこそ、日本の自然が育んだ誇るべきDNAではないのか。だから戦後の繁栄があったのではなかろうか。
中国五千年の権力闘争の歴史からくる自国民への不信感や、「恨(はん)」を抱えたまま南北がいまだ戦争状態にある朝鮮半島の現状を思うとき、日本人の本質が逆に浮かび上がってくる。
戦争中に日本は大陸および半島の人々に酷いことをした。それは原爆二つより過酷だったのかも知れないが、日本人は恨みを捨て、中国韓国は捨てずに燃やし続けている。そこには、敗戦国という理由だけでは説明できない何かがある。
この違いがどこから来るのかを深く考えていくことで、経済力を失ったあとの日本人のアイデンティティーが生まれてくるのではないだろうか。

ダイアモンド富士
高知新聞朝刊
作家・高樹のぶこ(たかぎ・のぶこ)
46年山口県生まれ。東京女子短大卒。
― posted by 大岩稔幸 at 06:53 pm
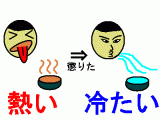



















Comments